1.気象病の正体
最近、
「なんだか体がだるい」
「頭が重い」「よく眠れない」
といった不調が続いていませんか?
病院に行っても「異常なし」と言われる場合、
それは気候の変化が原因かもしれません。
特に現代人の多くが抱える自律神経の乱れは、
季節の変わり目や天候の変化に
非常に敏感に反応します。
この気候による体調不良は「気象病」とも呼ばれ、
春の寒暖差、夏の高湿多湿、秋の急な冷え込みなど、
一年を通して私たちの心身を蝕んでいます。
2.気候が自律神経を乱す3つのメカニズム
なぜ、気候の変化が自律神経を乱すのでしょうか?
主なメカニズムは以下の3つです。
1.気圧の変化(特に低気圧)
天気が崩れる際に起こる気圧の低下は、
耳の奥にある「内耳」で感知されます。
内耳が気圧の変化を感じ取ると、
その情報が脳へと伝わり、
脳は「異常事態」と認識します。
この信号が、心身をコントロールする自律神経
(交感神経と副交感神経)のバランスを崩し、
頭痛やめまい、だるさといった
不調を引き起こすのです。
2.寒暖差の激しさ
季節の変わり目や、
室内外の温度差が激しいとき
(例えば夏のエアコンや冬の暖房)に、
体は体温を一定に保とうとフル稼働します。
この体温調節を担っているのが自律神経です。
頻繁な温度調整の要求は
自律神経に大きな負担をかけ疲弊させます。
特に、寒暖差が7℃以上になると、
自律神経の乱れが顕著になると言われています。
3.湿度と日照時間の変化
高湿度は、体内の水分調整を難しくし、
だるさやむくみを引き起こします。
また、日照時間の減少は、
精神の安定に関わるホルモン
「セロトニン」の分泌を抑制し、
気分の落ち込みや不眠を招き、
結果的に自律神経のバランスを悪化させます。
3.自律神経を整えるため今日からできること
気候の変化に負けない体を作るためには、
日常生活の中で自律神経を
意識的に整えることが重要です。
セロトニンを増やす(光と食事):
朝起きたらすぐに太陽の光を浴びる
(セロトニン分泌を促進)。
トリプトファン(肉、魚、大豆製品)を含む
食事を意識的に摂る。
内耳をケアする(耳のマッサージ):
内耳の血流を良くするため、
耳を優しく引っ張ったり回したりする
マッサージを毎日行う。
寒暖差から体を守る(緩やかな体温調整):
脱ぎ着しやすい服装で、
急激な温度変化を避ける。
特に首元、手首、足首を
冷やさないようにする。
ぬるめ(38~40℃)の入浴で、
副交感神経を優位にし、
体温を緩やかに上げる習慣をつける。
自律神経の乱れは放置すると、
慢性的な不調やより深刻な疾患に
つながる可能性があります。
季節や天候に左右されない、
健康的な毎日を取り戻しましょう。
この記事に関する関連記事
- 冬のメンタル不調は「季節のせい」ではありません!
- 「気圧のせい」と諦める前に。冬の不調を爆発させる「首の詰まり」と、自律神経の危険な関係
- なぜ背骨が歪むと免疫力が低下するのか?
- なぜ、冬になると不眠が増えるのか ―「心の問題」ではなく「体の条件」の話―
- ストレスと背骨の歪みの関係 ―「心の問題」で片づけられてきた不調の、本当の正体―
- その腰痛、原因は「骨」ではなく「胃腸の悲鳴」かもしれません。
- 寝ても疲れが抜けない原因は「背骨」の渋滞が原因?
- 「休めば治る」の嘘。起立性調節障害が、薬や生活指導だけで解決しない構造的理由
- 理由のない不安や緊張が消えない方へ。自律神経を整える鍵は「背骨の構造」に
- その「理由のない不安」、実は姿勢のせいです。脳を“危険モード”から救い出すカイロの視点
- うつ症状は「心の弱さ」ではない ──背骨が、あなたより先に限界を迎えているだけ
- 背骨の歪みが原因?不眠が続く本当の理由
- 雨の日に頭痛やだるさが出るのはなぜ?気圧と自律神経の乱れを整える方法
- 自律神経失調症が引き起こす「めまい」の正体と改善法
- 慢性腰痛が病院や整骨院で良くならない本当の理由とは?
- 自律神経失調、病院でなかなか改善しない理由とは?
- 迷走神経性失神が起こる原因とは?
- 背骨の歪みが“慢性疲労”をつくる理由とは?
- 原因不明のめまいは“背骨の歪み”から!
- 自律神経の乱れで免疫が低下する!
- 背骨の歪みが眠れない原因?自律神経と睡眠の深い関係
- 11月前半の体調不良に要注意!
- セルフチェックで気づく!自律神経失調のサインと対処法
- 寒暖差が7℃以上にご用心!自律神経の乱れが引き起こす不調と今日からできるセルフケア
- 背骨が歪むことで起こる「体・メンタル・スピリチュアル」の異常とは?
- あなたの症状、過去のストレスが原因かも?
- 背骨の歪みが睡眠の質を下げる理由〜自律神経と姿勢の深い関係〜
- 浅い呼吸が招く体と心の不調
- 秋の胃腸の不調…それ、「自律神経の乱れ」が原因?
- 秋の始まりに起こる頭痛の原因と対策 鶴橋で改善
- この時期に、風邪や不眠など体調不良が起こる原因とは?
- 脊柱管狭窄症と自律神経の関係 鶴橋で改善
- コンビニ弁当が続くと心が疲れる?精神的不調との関係 鶴橋で改善
- 最近、体調がおかしい方へ 鶴橋で改善
- PTSDと背骨の歪み― 心と体はつながっている 鶴橋で改善
- 自律神経と便秘の深い関係とは?
- ストレスが溜まることで体とメンタルに与える影響とは?
- 背骨の歪みと内臓の機能低下の関係
- トラウマが自律神経に与える悪影響!
- 自律神経失調 心と体に現れる不調の正体とは?
- 自律神経と呼吸の深~い関係 鶴橋の整体で改善
- 足がしびれるのはなぜ?原因と解決法を徹底解説
- 背骨が歪むことで起こる身体とメンタルへの影響
- 薬を飲んでも治らない頭痛 ― その本当の原因とは?
- ネガティブな記憶が身体とメンタルに与える悪影響とは?
- スマホ認知症になっていませんか? 鶴橋のカイロ整体
- 背骨の歪みと生理不順の深い関係とは?
- 休みの夕方になると頭痛がするのはなぜ? 鶴橋のカイロ整体
- 暑さと冷房のはざまで起こる体調不良とは? 鶴橋のカイロ整体
- カップラーメンが身体とメンタルに与える悪影響とは?
- 台風や気圧の変化で頭痛が起きるあなたへ|その原因と対策とは?
- 猛暑で自律神経が乱れる?暑さによる不調とその対策 鶴橋のカイロ整体
- 熱中症になりやすい人の特徴と対策 鶴橋のカイロ整体
- 「歩くこと」が体と心に与える意外な効果とは?
- 肩こりのつらさ、放っておくと危険な理由とその対策 鶴橋のカイロ整体
- 暑くなると自律神経の働きがおかしくなる理由とは? 鶴橋のカイロ整体
- 自律神経の乱れ、そのままにすると危険です! 鶴橋のカイロ整体
- 冷房による冷えが引き起こす体調不良の原因と対策 鶴橋のカイロ整体
- 梅雨になると体調が悪くなる、その原因と対策 鶴橋のカイロ整体
- 水を飲みすぎると危険?「水中毒」とは? 鶴橋のカイロ整体
- 湿度と気温の上昇で不眠になる原因とその解決策 鶴橋のカイロ整体
- 自律神経をセルフで整える5つの方法 鶴橋のカイロ整体
- 意外と知らない?梅雨型熱中症にご注意を 鶴橋のカイロ整体
- 天気が悪いとメンタルや体調が不安定になる理由と5つの解決法 鶴橋のカイロ整体
- 【天気が悪いと顔がむくむ理由とは?】 鶴橋のカイロ整体
- 【要注意】コンビニ弁当を続けると、体にこんな影響が…?
- ぐっすり眠るために朝に必要な5つの習慣とは? 鶴橋のカイロ整体
- 【眠れない夜に】質の良い眠りに必要な5つのこと 鶴橋のカイロ整体
- 季節の変わり目に起こる頭痛の原因とは? 鶴橋の整体
- 梅雨で体調が悪くなる原因と対処法
- 起立性調節障害とストレスの関係 鶴橋のストレスリセット整体
- 寝落ちが身体と自律神経に与える悪影響とは? 鶴橋のカイロ整体
- ストレスが抜けないあなたへ それ、自律神経の乱れが原因です!
- 子どものストレスによる体と心のサインとは? 鶴橋のストレスリセット整体
- 【デスクワーク疲れ】40代女性に多い「なんとなく不調」は自律神経の乱れが原因かも?
- 五月病の原因と今すぐできる3つの対策 鶴橋のカイロ整体
- 熟睡するための“ちょっと意外な習慣”とは? 鶴橋のカイロ整体
- 寒暖差による不調を防ぐには? 鶴橋のカイロ整体
- 子どものストレスサイン! 鶴橋のカイロ整体
- コンビニ弁当がもたらす体と心への影響とは? 鶴橋のカイロ整体
- つらい気象病とは? 鶴橋のカイロ整体
- スマホ首(ストレートネック)を放置するとどうなる? 鶴橋のカイロ整体
- 眠れない!それ姿勢の歪みが原因です。 鶴橋のカイロ整体
- 【5月に急増?】自律神経失調症 鶴橋のカイロ整体
- 五月病を防ぐためにゴールデンウィークにできること 鶴橋のカイロ整体
- 50代から増える身体の不調について 鶴橋のカイロ整体
- 4月に体調を崩しやすい理由とその対策? 鶴橋のカイロ整体
- 自律神経を整えるために必要なこととは? 鶴橋のカイロ整体
- 春の風邪に要注意! 鶴橋のカイロ整体
- 朝起きて頭が痛い!その問題と解決策 鶴橋のカイロ整体
- 自律神経失調症で悩むあなたへ 鶴橋のカイロ整体
- ストレスが引き起こす身体と心のSOS 鶴橋のカイロ整体
- 春先の自律神経の乱れに要注意! 鶴橋のカイロ整体
- デスクワークは腰痛以外にも要注意! 鶴橋のカイロ整体
- スマホが子供に与える悪影響! 鶴橋のカイロ整体
- お医者さんでは自律神経失調症は治せません!
- 元気になりたいのならこれをやってください!
- 気になる耳鳴り。その解決策とは?
- その体調不良、自律神経失調かも!
- めまいは自律神経の乱れから!
- その不調、隠れうつかも?
- う○ちが出ない!それ自律神経の乱れが原因です。~鶴橋のカイロ整体~
- つらい冷え性のあなたへ 原因・対策・自律神経との関係 ~鶴橋のカイロ整体~
- コンビニ弁当ばかり食べると精神が病む? ~鶴橋のカイロ整体~
- 60代女性の不眠の原因と解決策 ~鶴橋のカイロ整体~
- 睡眠不足で起こる身体の異常
- 気圧の変化で体調が悪くなる理由とは?
- 深く眠るための方法とは?
- 自律神経の失調を防ぐ方法とは?
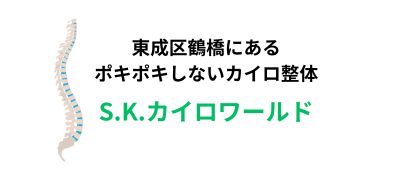







お電話ありがとうございます、
S.K.カイロワールドでございます。